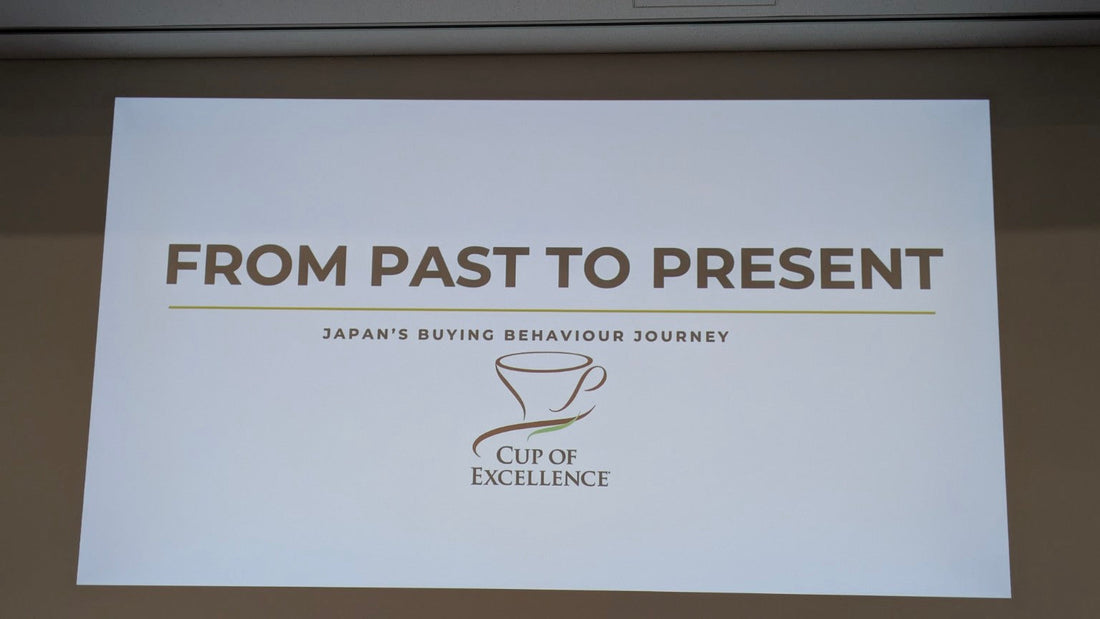
SCAJ2025レポート:Cup of Excellenceと日本の歩み
共有
SCAJ2025の会場にて、ACE(Alliance for Coffee Excellence)によるセミナー「From Past to Present: Japan's Buying Behaviour Journey」に参加いたしました。
私がコーヒーロースターとなるきっかけになった一杯のコーヒーは、2000年代初頭に飲んだブラジルのCoE入賞豆でした。その風味の素晴らしさに受けた衝撃については以前の記事でも触れましたが、今回のセミナーではあの時の記憶を思い出しながら、CoEが業界の一つの指針として産地とマーケットに寄与してきたことを改めて実感いたしました。カッピングや品評の現場ではなかなか見えにくい、「仕組み」としてのスペシャルティコーヒーの裏側を垣間見る貴重な機会でした。

Cup of Excellence(CoE)とは
CoE(Cup of Excellence)は、1999年にスタートした国際的なコーヒー品評会です。各生産国で開催され、その年に収穫された最高品質のロットを選び、国際的な評価基準と透明性のあるプロセスを経てオークションで販売します。これまでに9,000万ドル(約132億8千万円)以上を調達し、その金額の75-80%が直接生産者に還元されています。まさに「生産者からカップまで」という理念を体現するシステムといえるでしょう。

競技会の透明性と厳格さも特筆すべき点です。事前選考から始まり、12-14名の国内審査員による約3,600杯のカッピング、そして国際審査員による最終審査まで、合計8,720杯のカッピング!を通じて各国の最高品質コーヒーが選出されます。たった300キロ程度の小規模ロットでありながら、大手ロースターがコンテナ単位で購入する際の10杯程度である実情とは比較にならない厳密な評価を受けているとのことです。その上で、単に品質を競う大会ではなく、「努力に見合う対価が支払われる仕組み」として、17の生産国の生産者が経済的にも恩恵を受けています。
日本とCoEの歩み:1999年から2025年へ
日本は1999年の第一回目から重要な存在感をもって参加してきました。2000年代初頭には全体の約75%、2010-2018年頃には約50%、そして現在は約35%のシェアを占めています。数字上は減少傾向に見えますが、これは市場の多様化と成熟を意味しているといいます。セミナーの中では、日本がCoEにおいて果たしてきた役割の変遷が度々詳しく紹介されました。 私の個人的な印象としては直近ではコロナ禍の影響が大きくその後の円安傾向もあって、以前と比較して日本の購買力の低下が伺える内容となっていると感じました。

購買パターンの変遷
- 1999〜2018年:日本はCoEの創設期を支えた主要購買国。大量購買によってプログラムを安定化させ、品質文化の形成に貢献。
- 2019〜2025年:プレミアム性を重視した選択的な購買へ移行。少量ロットでも継続性・信頼性のある購買スタイルへ。
特に注目すべきは、日本の買い手が始めた「グループ購入」システムです。中小規模のロースターが複数でグループを組み、一つのロットを共同購入することで、少量でも高品質なコーヒーを調達できるようになりました。この仕組みは現在、韓国、ノルウェー、オーストラリアなど世界各国に広がっているそうです。
市場動向の変化と現在の傾向
近年の日本市場の動向には興味深い変化が見られます。2018年から2025年の期間を見ると、購入ロット数は減少していますが、平均価格は上昇傾向にあります。これは「量から質へ」の転換を示しており、日本の消費者とロースターがより精緻な選択を行うようになったことを物語っています。現在は台湾・韓国・中国などのマーケットが価格競争の先頭に立つ一方で、日本はクリーンで安定した品質を評価する存在として信頼されています。
品種の好みにも変化が見られます。2018-2019年はブルボン種(ブラジルの伝統品種)が人気でしたが、2020-2021年にはティピカ種(コーヒーの原種に近い品種)、そして2022年以降はゲイシャ種(エチオピア原産の希少品種)への注目が高まっています。味わいのプロファイルも、かつての「洗練されたバランス」から、現在は「エレガントでエキゾチック」な方向へと変化しています。
カフェ文化と物語性のある購買
2010年代以降、日本国内でもサードウェーブ系のカフェが増え、トレーサビリティ、つまり「背景の見えるコーヒー」への関心が高まってきました。ストーリーや作り手への共感を重視する姿勢は、アジア全体での消費スタイルの変化と重なります。これは私たちロースターにとって、価格競争ではなく価値提案の重要性を示しています。産地のストーリー、生産者の情熱、精製方法の特徴、そして焙煎によって引き出される風味の変化—これらすべてを丁寧にお伝えすることが、真のスペシャルティコーヒー体験につながるのだと改めて感じました。

2019年には、日本のコーヒー消費量は年間750万袋(60kg袋換算)に達し、世界有数のコーヒー消費国としての地位を確立。市場としての存在感も、国際的に注目され続けています。
日本の現在位置:量から質への転換
日本は現在、ボリュームバイヤーから「洗練されたキュレーター」へと役割を変化させていると言います。セミナーで印象的だったのは、Mary氏が語った「日本の消費者は訓練されている」という言葉です。確かに、お客様との会話の中で感じるのは、「高い値段だから良いコーヒー」ではなく、「なぜこのコーヒーが特別なのか」を理解しようとする姿勢です。
購入量は減少傾向にある。この変化は決してネガティブな側面のみを意味するものではありません。むしろ、日本のコーヒー文化の成熟度を示すものであり、世界のスペシャルティコーヒー市場における「品質の指針」としての役割を担っていることを意味していると氏は言います。韓国、台湾、中国といった新興市場が価格競争の牽引役を担う中、日本は品質と一貫性を重視する成熟したマーケットとしての地位を確立しつつあります。またCoE以外のコンペティションも増えていることにも言及されていました。
ボタリズムとしての学び
今回のセミナーを通して、私はあらためて「なぜこの仕事をしているのか」という原点に立ち返るような感覚を覚えました。私自身がCoE入賞豆に魅了されたのは、その完璧なまでのクリーンカップ(雑味のない澄んだ味わい)と、産地の個性が鮮明に表現されたテロワール(土地の特徴を反映した風味)でした。口内に驚くほど広がる豊かな風味と、いつまでも続くような長い長い余韻に感動したことを今でも鮮明に思い出します。
Cup of Excellenceは単なるコンテストではなく、一粒のコーヒー豆が世界とつながる道筋を丁寧に照らす仕組みです。生産者の努力、透明な評価、継続的な品質向上のサイクル、そしてそれを信じて支える人々の存在。これらを具体的な事例と数値をもって目の当たりにしたことで、「一杯の背後にある膨大な時間と意志そして志し」に深く心を打たれました。
私たちロースターが焙煎する豆も、どれ一つとして偶然に手元へ届くものはありません。どのようなプロセスで収穫され、どう評価され、どんな経緯で輸送されてきたのか。その背景に関心を持ち、理解を深めていくことで、その豆の価値をきちんと伝える一杯が生まれるのだと、あらためて実感しています。
南房総という自然豊かな環境でロースターを営む中で、生産者の努力と想いが込められたコーヒーを丁寧に焙煎することの意味を日々実感しています。CoEのようなプログラムが、生産者とロースター、そして最終的にはお客様との間に築く「つながり」こそが、スペシャルティコーヒーの真の価値なのではないでしょうか。
Botarhythmでは、こうした学びを自分自身の感性と重ねながら、どのコーヒーにも背景と物語が宿るようなコーヒー体験を目指しています。技術や情報のアップデートはもちろん、お客様との対話の中で伝える言葉にも、その想いを込めて。これからも学び続け、コーヒー産地との架け橋として、静かに、確かに歩みを続けていきたいと思います。
